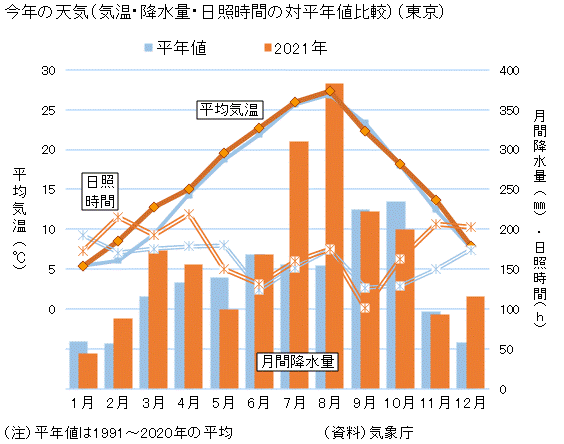人間はつい単純化してしまいがちな生き物であって、おそらくは複雑なものを複雑なまま捉えるということがとても難しいからだろう。
学問方面の「理論」というのもおそらくは単純化のためである(というのまとめ方も単純化だ)。理論によって単純化することによって、理解しやすくなったり、理論を展開しやすくなったりする。
しかしまあ、単純化が全てバンザイ! というわけにはいかなくて、中には「これはイタい」と思わせる単純化や、時に害悪ではないか、という単純化もある。そうした例をいくつか挙げてみたい。
1. 日本人は農耕民族
ワハハ。いきなり出た。
どういうわけか、こういう捉え方をする人は少なくない。「日本人は農耕民族だから〇〇する」。その対として、「欧米人は狩猟民族だから〇〇する」というふうに話を展開することが多い。ネットで「農耕民族」と検索してみれば、この手の話はわんさと出てくる。
しかし、イタい、というか、間抜けな捉え方である。
まず日本人が農耕民族だとしたら、漁師さんをどう考えればよいのだろう。マタギはどうなるのか。
まあ、昔は百姓の割合が多かったので日本人は農耕民族だった、と百歩ゆずって認めるとしても、中国人は、韓国人は、タイ人は、インド人は、どうなるのだろう。おれの知る限り、彼らも農耕をする人が多かったはずだ。としたら、彼らと日本人は同じ性向を持っていることになる。持っていたっていいが、世界中は農耕民族だらけで、とても農耕民族だから云々という話はできないんじゃないか。
欧米人が狩猟民族という話もどこから出てきたんだろう。そりゃまあ、二千年前、三千年前は知らないが、おれの知っている限り、フランス人だって、ドイツ人だって、イギリス人だって、イタリア人だって、随分昔から農耕しているぞ。
2. 「海外では」
さっきの農耕民族バナシにも似ているところがあるんだが、簡単に「海外では〜」と言い出す人がいる。
海外、と言ってもたいていは欧米の、それも先進国と言われる国の話であって、中国も、韓国も、タイも、ラオスも、インドネシアも、フィリピンも、モンゴルも、パキスタンも、バングラディシュも、インドも、ネパールも、イランも、アフガニスタンも、アラブ首長国連邦も、サウジアラビアも、イラクも、エジプトも、チュニジアも、モロッコも、スーダンも、ケニアも、コンゴも、ナイジェリアも、セネガルも、南アフリカも、アンゴラも、メキシコも、キューバも、パナマも、コロンビアも、ブラジルも、エクアドルも、ペルーも、チリも、アルゼンチンも、ベネズエラも、「海外」に含まれることはない。
日本は島国であるからして、文字通りにとらえれば、日本以外の国は全て「海外」になるはずなんだが、なぜだか、「海外では〜」と言うと、欧米の先進国を指してしまう。黒船以来の呪縛だろうか。
しかも、欧米先進国といったって、いろいろなはずなんだけどな。
3. 国際金融資本黒幕論
何か歴史的な事件が起きると、「国際金融資本(しばしばユダヤ系金融資本とも呼ばれる)が黒幕である」というストーリーが飛び出す。なぜか結構な人たちを惹きつけるようだ。
国際金融資本なるものがなんらかの活動をしているのはまあ、そうなんだろうが、「黒幕」という決定的な働きをしているのか、あるいはできるのかは甚だ疑問である。
世の中にはいろんな勢力がいて、それぞれの思惑でさまざまな活動をしている。影響力の強い勢力もあれば、そうでもない勢力もある。それらが互いに働きかけをしあって、ちょうどコックリさんを大勢でやるようにして動いているのが世の中だろう。
それを、「国際金融資本が黒幕である」で片付けるのはいかにも単純化であり、乱暴である。もっと言うと、間抜けである。
他にもいろいろとイタい単純化はあるんだが、今日はここまでにしておこう。
あ、マルクスさんの「階級闘争」というのもえらい単純化ですね。昔は随分と惹きつけられた人もいたみたいだが、単純化したものを真に受けるとひどい目に合うといういい例だと思う。